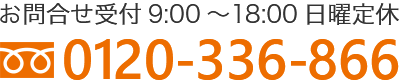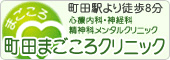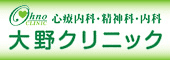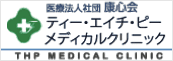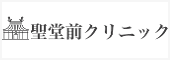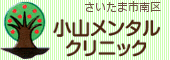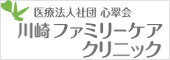- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- 就労移行支援とは
- 障がい福祉サービスを受けるために必要な「受給者証」とは
- 診断書とは?内容や受け取り方法、必要になるケースなど徹底解説!
診断書とは?内容や受け取り方法、必要になるケースなど徹底解説!
診断書とは
診断書は、医師が患者を診察し、病状や診断結果をまとめた文書です。患者の基本情報、診断内容(病名や症状)、治療内容などが記載されています。病気やケガであることを客観的に証明する書類です。
診断書を使用する場合は、主に以下のとおりです。
- 会社への提出
病気やケガで仕事を休む場合、会社から提出を求められることがあります。診断書によって、病気やケガであることを客観的に証明できます。 - 保険会社への提出
保険金を請求するときに、診断書が必要な場合があります。診断書に基づき、病気やケガの程度を判断し、それによって保険金が支払われたりします。 - 行政への各種申請
障がい者手帳や障がい年金の申請など、行政への申請手続きに必要になることがあります。自己申告ではなく、医療の専門家である医師の診断書の提出が求められます。
診断書の発行は、診察を行った医師が行います。発行には費用がかかることが多く、費用は、医療機関によって異なります。
診断書が必要な3つのケース
【ケース①】 精神疾患・病気などによる休職
精神疾患や病気によって仕事が困難になった場合、会社に休職を申し出る際に診断書が必要になることがあります。会社に提出する診断書には休養期間の記載を求められることがあるため、どのような内容の診断書が必要かを事前に会社に確認し、その上で医師に診断書の作成を依頼しましょう。実際に休職する場合は、診断書に記載された休養期間を参考に、会社と相談して休職期間を決めます。
なお、休職制度は、法律で決まっているものではなく、それぞれの会社が就業規則などで定めています。そのため、休職できる期間や条件は会社によって異なります。休職制度の利用を検討する際には、必要な診断書の内容や休職できる期間など、会社の窓口に確認しておくと安心です。
【ケース②】 精神疾患・病気などによる業務内容の調整
精神疾患や病気により、今の業務をそのまま継続することが困難になった場合、診断書の内容をもとに、業務内容を調整してもらえることがあります。
診断書には、病名、現在の症状、治療内容などが具体的に記載されます。これにより、会社は従業員の病状を正確に把握し、業務内容の調整や、より適切な働き方への転換を検討することができます。例えば、業務量を減らしたり、担当業務を変更したり、あるいはリモートワークを導入したりといった、従業員が無理なく働けるような環境を整えるための具体的な対策を講じることができます。
ただし、会社がどのように対応するかは、個々のケースによって異なります。そのため、いきなり診断書を提出するのではなく、まずは上司などに相談し、どのような対応をしてもらえるか聞いてみましょう。その上で、診断書の提出を求められたときは、医師に診断書の作成を依頼しましょう。
【ケース③】 福祉制度の利用
診断書は、病気やケガの状態を証明する書類として、様々な福祉制度を利用する際に必要となることがあります。具体的には、以下の様な場合に診断書が必要となることがあります。
| 障がい者手帳の申請 | 障がいの種類や程度、日常生活への影響が記載された診断書が必要になります。診断書の内容に基づき、障がい者手帳の等級等が判定されます。 |
| 障がい年金の申請 | 障がいの程度や日常生活能力や就労状況など、年金受給の基準を満たしていることを証明するために診断書を提出します。 |
| 自立支援医療(精神通院医療)の申請 | 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患による医療費の自己負担を軽減するための制度で、診断書はその適用を判断するために重要です。 |
これらの診断書は医師に作成を依頼します。ただし、各種制度で診断書の様式や記載内容が異なるため、制度ごとに適切な診断書が必要です。診断書の有効期限も確認しておくとよいでしょう。詳細な情報は、お住まいの自治体の相談窓口で確認できます。
診断書が必要とされる理由とは
診断書は、医師が医学的な見地から患者の状態を客観的に記述した重要な文書です。単なる病名だけでなく、病状の経過、現在の状態、治療内容、日常生活への影響などが記載されています。これにより、医療関係者間での情報共有や、適切な医療サービスの提供に役立ちます。
また、診断書は医学的な情報伝達の手段としてだけでなく、社会保障制度や福祉サービスを利用する際の客観的な証明書としても用いられます。例えば、障がい者手帳の申請では、診断書に基づいて障がい等級が認定されます。障がい年金の申請においては、診断書に記載された日常生活や就労に関する内容をふまえて、年金受給の可否などが判断されます。
診断書はどのような内容(様式)なのか
診断書の様式は、一概に「これ」といった決まった形があるわけではありません(提出先によっては、所定の様式が決まっている場合があります)。目的や提出先によって必要な情報が異なるためです。一般的には下記のような項目が診断書には記載されています。
- 医療機関の情報
- 患者の個人情報
- 病名、病状
- 治療内容
- 検査結果 など
このような基本情報に加えて、診断書の用途や種類によって、さらに詳細な情報が記載されることもあります。例えば、障がい者手帳の申請に使用する診断書であれば、初診日や発症から現在に至るまでの経過、現在の生活能力の状態などが記載されます。
また、障がい年金の申請に使用する診断書には、障がいの状態に関する内容に加え、現在の就労状況なども記載されます。
診断書は、提出先や用途によって記載内容が異なります。そのため、診断書の作成を医師に依頼するときは、目的と提出先を明確に伝えることが非常に重要です。そうすることで、医師は適切な情報を記載した診断書を作成することができます。どのような様式の診断書が必要になるか分からないときは、提出先に確認してみましょう。
診断書の内容を希望のものにできるのか
診断書は、医師が客観的な情報に基づいて作成するものであるため、患者の希望通りの表現になるとは限りません。医師は診察や検査の結果に基づいて、病名や症状、治療内容などを正確に記載する責任があります。
医師に正確な診断書を作成してもらうために、診察時に自分の状態を正しく伝えられるよう、あらかじめ話す内容を整理しておくとよいでしょう。
診断書を作成してもらうための費用や時間はどのくらいかかるのか
診断書の作成に費用が発生するイメージがない方もいらっしゃるかと思います。
結論から言えば、費用が発生します。
診断書の様式がそれぞれ異なるため、様式によっても費用が異なります。
また、同じ様式であっても病院によって費用が異なる点にも注意が必要です。
費用は、診断書の記載内容にもよりますが、おおよそ2,000円〜10,000円程度となります。
診断書の作成・発行にかかる日数も、病院や診断書の様式によって異なりますが、数日程度のケースから3週間ほどかかるケースもあります。
診断書の費用(料金)が高くなるケースについて
診断書の料金は医療機関によって異なりますが、一般的には数千円~1万円前後です。診断書の内容が簡単なものや医療機関の所定様式であれば比較的安いですが、複雑になれば高くなる傾向があります。例えば、障がい者手帳や障がい年金の申請用診断書など、詳細な記載が求められる場合は、料金が高くなることがあります。同じ内容の診断書を複数枚発行してもらう場合も、枚数に応じて料金が加算されることもあります。具体的な料金について気になる方は、事前に医療機関のホームページなどで確認してみましょう。
診断書を書いてもらうには
診断書はどこで作成してもらえるのか
診断書は、医師が診察をした上で作成する文書です。病院やクリニックなどの医療機関で作成してもらうことができます。かかりつけ医がいれば、まずはその医師に相談するとよいでしょう。その際には、使用目的、提出先を明確に伝えることで、必要な情報が記載された診断書を作成してもらえます。かかりつけ医がいない場合は、症状に応じた医療機関に相談してみましょう。また、大きな病院などでは、診断書を発行するための専門窓口を設置していることもあります。
診断書を作成するのにどれくらいかかるのか
診断書の作成にかかる時間は、医療機関や診断書の内容によって異なります。簡単な内容であれば、当日中に発行してもらえる場合もありますが、詳細な記述が必要な場合などは、数日から2週間前後かかる場合もあります。あらかじめ、どのぐらい時間がかかるのか、医療機関に確認しておくと安心です。また、提出期限を確認し、余裕をもって診断書の作成を依頼するようにしましょう。
診断書がもらえないケースはあるのか
診断書は、医師が医学的な判断に基づいて作成するものです。そのため、医療機関に依頼すれば必ず作成してもらえるとは限りません。以下のような場合、診断書をもらえないことがあります。
- 診察の結果、病気や症状が認められなかった場合
- 診断書を求める目的が不適切だと判断された場合 など
医師は、虚偽の診断書を作成することはできません。そのため、実際の病気・症状と異なる診断書を求めることはやめましょう。
診断書に有効期限はあるのか
診断書の有効期限は、提出先によって異なります。例えば、障がい年金の申請に使用する診断書は提出日から3ヶ月以内に作成されたものである必要があります。症状は時間とともに変化する可能性があるため、診断書の作成から時間が経ってしまうと、現在の状態を反映していないものになってしまうからです。診断書を提出する際には、事前に提出先に有効期限を確認し、期限内に発行された診断書を提出するようにしまよう。もし、有効期限が切れてしまったら、再度医療機関を受診して作成を依頼する必要があります。
診断書を会社へ提出して休職する際の3つのポイント
診断書を提出して休職する際には、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
【ポイント①】 会社によって休職の制度は異なる
会社を休職する場合、まず自社の就業規則などを確認しましょう。休職できる期間や休職中の給与や社会保険の取扱いなど、会社によって制度は異なります。なぜなら、法律で定められているのは育児・介護休業のみで、病気などによる休職制度の取扱いは、それぞれの会社に委ねられているからです。そのため、休職制度を設けていない会社もあります。
休職を検討する際には、自社の規定をよく確認し、不明な点は担当者に問い合わせましょう。また、休職する際には、診断書だけではなく、休職申請書などの提出を求められることもあります。事前に必要な書類、手続きを確認しておくとスムーズです。なお、休職中であっても、基本的には社会保険料の支払いが発生します。休職中の社会保険料の支払い方法についても、確認しておくとよいでしょう。
【ポイント②】 傷病手当金が受け取れるかどうか確認する
休職中に給与が支払われない場合、健康保険から「傷病手当」が支給される可能性があります。傷病手当は、病気やケガで仕事ができないときに、生活を保障するために支給されるものです。以下の条件を満たすと傷病手当を受け取ることができます。
- 業務以外の病気やケガで療養中であること
- 病気やケガで仕事ができない状態であること
- 連続する3日を含み、4日以上仕事ができないこと
- 給与の支払いがないこと
支給される傷病手当は、休職前に受け取っていた給与の、おおよそ2/3ほどです。また、支給を開始した日から最長1年6ヶ月において受け取ることができます。
傷病手当の申請には、医師の診断書以外にも事業主の証明書などが必要です。詳しくは加入している健康保険組合や協会けんぽに問い合わせましょう。
【ポイント③】 休職時はとにかく休む
診断書を提出し、休職が認められたら、まずはしっかりと休養に専念しましょう。仕事のことは一旦忘れ、心身の回復を最優先に考えます。休職期間は、治療に専念し、心身の状態を整えるための大切な時間です。焦って復職を考える必要はないので、医師の指示に従って治療に専念しましょう。
休職中は、生活リズムを整え、規則正しい生活を送るように心がけてください。適度な運動やリラックスできる時間を持つことも大切です。
復職時期については、主治医と相談しながら慎重に判断しましょう。焦って復職すると、症状が悪化してしまう可能性もあります。十分な休養を取り、心身ともに回復してから復職することが大切です。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
日暮里Office
🌸🌸日暮里office🌸🌸 事業所説明&見学について!! -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第2Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
北朝霞Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中
Officeブログ新着情報
-
新板橋駅前Office 2025/04/01
プログラム紹介【書類郵送のマナーとお礼状の書き方】 -
目黒駅前Office 2025/04/01
【Cocorport目黒駅前Office】「日直」係の紹介! -
千葉Office 2025/04/01
【プログラム紹介】JST・上司からの指示を受ける🧑🏻💼📝 -
川越第3Office 2025/04/01
就職者インタビュー -
相模原橋本Office 2025/04/01
プログラム紹介~ウォーキング🌸春の花を探しに~ -
京都四条河原町駅前Office 2025/04/01
🌸桜を見に行こう🌸 -
日暮里Office 2025/04/01
🌸「伝わりやすく話す🗣️」ことに自信がありますか??🌸 -
国分寺駅前Office 2025/04/01
🏵️🌺Office内ツアーpart2🌺🏵️ -
湘南藤沢Office 2025/04/01
🌸スケジュール管理の工夫🌸 -
八王子駅前Office 2025/04/01
桜の時期🌸4月:おすすめプログラム