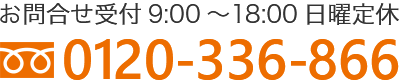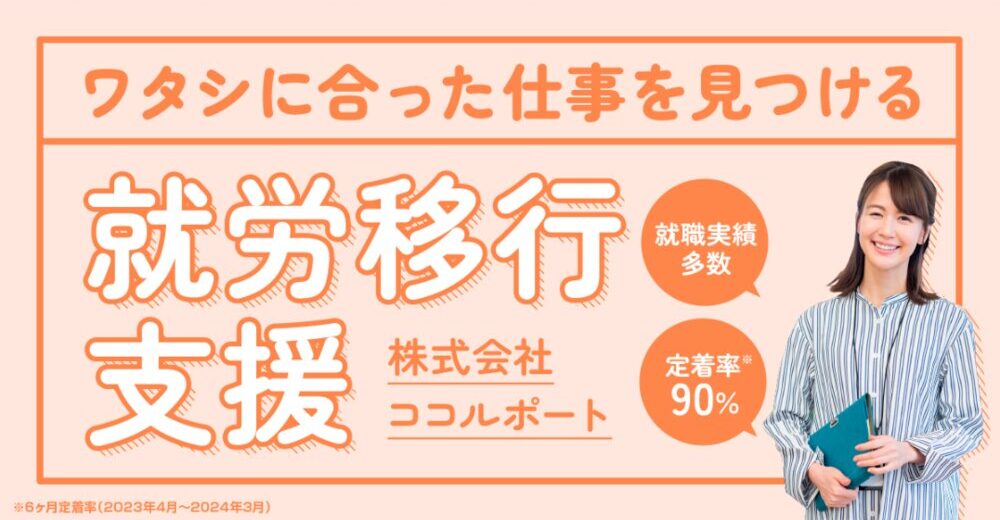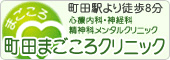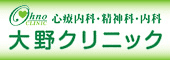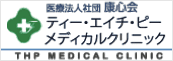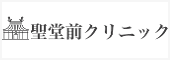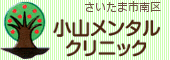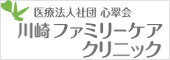- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- ADHDに注意欠陥のみのタイプはある?特徴や就労におけるポイント
ADHDに注意欠陥のみのタイプはある?特徴や就労におけるポイント
公開日:2025/04/21
更新日:2025/04/24

ADHDの方は、不注意によるミスや集中力の維持の難しさから、日常生活や仕事の場面で困りごとが生じるケースが多々見られます。また「多動や衝動性はないが、忘れっぽくて仕事がうまくいかない」「締め切りを守るのが苦手で、職場で評価が下がってしまう」といった悩みを持つ方もいるでしょう。
この記事では、かつて「ADD(注意欠陥障がい)」と呼ばれていた「不注意優勢型ADHD」の特性や、ADHDの中での位置づけ、就労における困りごととその対策などについて詳しく解説します。
目次
ADD(注意欠陥障がい)とは?
ADD(注意欠陥障がい)は、不注意や衝動性を特徴とする発達障がいの一種です。
現在では「ADD」という診断名は使われておらず、「ADHD(注意欠如・多動症)」という名称に統一されています。
初めてADDという診断名が使われたのは、1980年に出版されたDSM-Ⅲ(精神疾患の診断基準)です。それ以前の診断基準では、主に多動性に焦点が当てられていましたが、改訂によって「注意の持続の困難」や「衝動性の制御の問題」にも注目されるようになりました。
ADDという言葉は今でも非公式に使われることがあり、特に保護者や教育現場などでは、ADHDの中でも「多動が目立たない」場合に「ADD」と表現されることがあります。しかし、診断上および保険上は「ADHD」が正式名称であり、「ADD」は使用されません。ADDは正式な診断名ではなく、現在は「ADHD」という名称に統合されています。
ADHD(注意欠如・多動症)には3つのタイプがあり、そのうち「不注意優勢型ADHD」がADDに該当します。臨床的にも診断的にも「ADHD」の枠組みで理解・対応することが推奨されます。
ADHD(注意欠如・多動症)には3つのタイプがあり、そのうち「不注意優勢型ADHD」がADDに該当します。
ADHD(注意欠如・多動症)とは

ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障がいの一種で、不注意、多動性、衝動性が主な特徴です。症状は幼少期から見られることが多く、日常生活や社会生活に影響を及ぼすことがあります。
ADHDは大きく「不注意優勢型」「多動・衝動優勢型」「混合型」の3つのタイプに分類され、それぞれ特有の傾向が見られます。タイプ別に詳しく見ていきましょう。
不注意優勢型
不注意優勢型は、集中力の維持が難しく、物事の優先順位を付けることが苦手な傾向があります。重要な用事や締め切りを守れず、結果として周囲から「だらしない」「責任感がない」と誤解されやすいです。
さらに、一つのことに集中することが難しく、宿題の途中でテレビやスマートフォンに気を取られたり、仕事中に他のタスクへ注意が向いてしまい、結果として作業が滞ったりすることもあります。
忘れ物が多いのもこのタイプの特徴です。子どもの場合は学校に必要なものを持参し忘れたり、親に渡すべき書類を忘れたりすることがよくあります。大人になると、鍵や財布、日用品などを頻繁になくし、約束や会議のスケジュールを忘れてしまうことが増えます。
多動・衝動優勢型
多動・衝動優勢型は、じっとしていることが苦手で、常に体を動かしていたり、思いついたことをすぐに行動に移したりする傾向があります。子どもの場合、椅子にじっと座っているのが難しく、机や椅子を揺らす、何かを触っていないと落ち着かないといった行動が多く見られます。
大人になっても、無意識に貧乏ゆすりやペンをカチカチ鳴らすといった行動をします。また、多数の議題がある会議において大きなストレスを感じ、衝動的に会議室を飛び出してしまうことも多動・衝動優勢型の行動例の一つです。
混合型
混合型は、不注意優勢型と多動・衝動優勢型の特徴を併せ持つタイプです。会話の途中で相手の発言を遮ってしまったり、思ったことをすぐに口にしたりします。
そのため、周囲とのコミュニケーションがうまくいかず、トラブルにつながることもあります。また衝動的な行動が目立ち、例えば欲しいものがあると衝動的に購入します。
さらに、感情のコントロールが難しく、自分の思い通りにならないとすぐにイライラすることも特徴です。子どもの場合は、些細なことでかんしゃくを起こし、大声を出したり、物に当たったりします。大人になっても、自分の感情をうまく抑えられず、人間関係で摩擦が生じることがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)とADD(注意欠陥障がい)との違い
ADHD(注意欠如・多動症)とADD(注意欠陥障がい)は、かつては異なる名称で分類されていましたが、現在ではADHDという診断名に統一されています。両者の違いは、「多動性」や「衝動性」があるかどうかです。
ADDは、不注意の症状が目立つものの、多動性や衝動性がほとんど見られないタイプで、現在では「不注意優勢型ADHD」として分類されています。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の特性による日常や就労での困りごと
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の特性のある方は、日常生活や仕事の場面で、忘れっぽさや集中力の維持の難しさによって、さまざまな困りごとを抱えることがあります。
例えば、日常や仕事において、以下のような問題が生じます。
| 日常での困りごと | 就労に関する困りごと |
|
|
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の特性による二次障がいとは
二次障がいは、本来の特性が原因で引き起こされる精神的・身体的な問題のことです。ADHDやADDの特性は、本人の努力だけでは克服しにくい側面があるため、日常生活や人間関係の中で強いストレスを感じる方が多く見られます。
ストレスが長期的に蓄積されると、心や体にさまざまな影響が現れます。
二次障がいには、大きく分けて「内在化障がい」と「外在化障がい」の2つのタイプがあります。それぞれの特徴と症状の例は下記の通りです。
| 障がいの種類 | 説明 | 例 |
| 内在化障がい | ストレスや問題が自分の内側に向かい、精神的な症状として現れる |
|
| 外在化障がい | ストレスが他者や環境に向かい、行動上の問題として現れる |
|
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の要因
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の原因は、明確に分かっていません。注意力や衝動の制御を担う前頭葉や、行動の調整に関与する線条体などの脳領域において、ドーパミンという神経伝達物質の働きが関係しているとの報告があります。
かつては、ADHDの特性が親のしつけや教育環境の影響によるものではないかという考え方もありましたが、近年の研究によって否定されています。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の診断を受けるには?
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の診断は、精神科や心療内科で受けられます。しかし、全ての医療機関が発達障がいの診断に対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
また全国に設置されている「発達障がい者支援センター」では、ADHDを診察できる医療機関の情報を提供しているため、事前に相談しても良いでしょう。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)は、アメリカ精神医学会が定めた「DSM-5」の診断基準を基に行われます。診断方法は、医師による問診が中心ですが、必要に応じて知能検査などの心理検査を行います。
問診をスムーズに進めるために、仕事でどのようなミスが多いのか、日常生活でどのような困難を感じているのかなど、事前に自分が困っていることを整理し、メモを取っておくと良いでしょう。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の治療
不注意優勢型ADHD(旧ADD)は、生まれつきの脳の特性によるものであり、現在の医学では完全に治すことはできません。しかし、適切な対策を取ることで、日常生活や仕事での困難を軽減できる場合があります。
主な方法として、「環境調整」と「薬物療法」の2つが挙げられます。
環境調整は、ADHDの特性を考慮し、できるだけ集中しやすく、ミスを減らせる環境を整えることです。例えば、注意がそれやすい場合には、仕事や勉強をするスペースを静かな場所に設定したり、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンで周囲の音を遮断したりします。
また予定やタスクを目に見える形で管理することも大切です。スマートフォンのリマインダー機能や付箋を活用し、やるべきことをすぐに確認できる状態にしておくと、忘れ物や予定の抜け漏れを防げます。
薬物療法は、不注意優勢型ADHDの症状を緩和し、日常生活や仕事をよりスムーズに進めるための補助として用いられます。環境調整による対策が優先され、それでも十分な効果が得られない場合に薬の使用が検討されます。
ADHDに使用される薬にはいくつかの種類があり、それぞれ効果や持続時間、副作用の有無が異なります。薬の効果には個人差があるため、医師と相談しながら、自分に合ったものを見つけることが重要です。以下で述べる生活での工夫が優先されますが、それでも日常生活に困るようであれば、薬物療法を行った方がよい可能性があります。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の方が働き続けるために大切なこと
不注意優勢型ADHD(旧ADD)の方にとって、働き続けることはさまざまな困難を伴う場合があります。しかし、適切な環境調整や仕事の進め方を工夫することで、負担を軽減し、安定して働くことが可能です。
不注意優勢型ADHDの方が職場で長く働き続けるためのポイントを紹介します。
職場の理解を得て就労環境に配慮してもらう
ADHDの特性について周囲に話すことに抵抗がある方もいますが、職場の理解を得ることで働きやすい環境を整えられるでしょう。全てを話す必要はなく、「集中しにくいので静かな環境があると助かる」「一度に複数の指示を受けると混乱してしまう」といった具体的な要望を伝えることで、適切な配慮を受けられる可能性があります。
例えば、オープンスペースのオフィスではパーテーションを設置することで視界を遮り、集中しやすい空間を作ることが可能です。また耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの使用を許可された場合には、周囲の雑音を減らし、仕事に集中できる環境を整えられます。
さらに、一度に複数の業務指示を出さず、一つずつ順番に指示されることで混乱を防ぐといった配慮や、業務の進捗を確認するための声掛けを定期的にしてもらうなどの方法もあります。
※参考:厚生労働省「発達障がいのある方への職場における配慮事例のご紹介」
TODOリストを活用する
仕事の優先順位を付けるのが苦手な場合、TODOリストを活用することがおすすめです。TODOリストとは、やるべきことをリスト化し、順番にこなしていく方法のことです。
まず、やるべき仕事を全て書き出し、その後で優先順位を付けます。急ぎの業務は目立つようにマークを付けたり、期限を明確にしたりすることで、作業の遅れを防げます。
TODOリストの作成方法には、紙に書く、スマートフォンのアプリを使う、パソコンのタスク管理ツールを利用するなどさまざまな方法があるため、自分に合ったものを選ぶことがポイントです。
メモを取る習慣を付ける
仕事中に指示を聞き逃したり、会議の予定を忘れてしまったりすることが多い場合、メモを取る習慣を付けることが大切です。不注意優勢型ADHDの方は情報を記憶することが難しい場面が多いため、その場で記録することを習慣化することで、忘れ物や抜け漏れを防止できます。
メモを取る際は、持ち歩きやすい小さなノートや手帳を用意すると便利です。また、スマートフォンのメモアプリを活用するのも一つの方法です。
規則正しい生活をする
生活習慣が乱れると、気分の浮き沈みが激しくなったり、仕事のパフォーマンスが低下したりすることがあるため、規則正しい生活を心掛けることが大切です。
特に睡眠のリズムを整えることは、集中力を高めるために重要です。毎日決まった時間に寝る習慣を付けることで、脳の働きを安定させ、日中の活動をスムーズにできます。
また適度な運動を取り入れることも、ADHDの症状を緩和する助けになります。ウオーキングや軽いストレッチをすることで、気持ちが落ち着き、集中力が向上する効果が期待できます。食生活においても、血糖値が急激に上下しないようにバランスの取れた食事を心掛けることで、注意力の維持に役立ちます。
強みを生かした仕事を見つける
ADHDやADDは、一般的に「不注意」や「衝動性」といった課題ばかりが注目されがちですが、それと同時に強みも持っています。
興味を持ったことには高い集中力を発揮する、独創的な発想ができる、ルーティンワークよりも変化のある環境で力を発揮しやすいといった特徴を生かせる仕事に就くことで、ADHDの特性を強みに変えられます。
例えば、興味関心のある分野では探究心を発揮できるため、研究職やクリエイティブな仕事が適している場合があります。
また想像力を生かせる仕事も、ADHDの特性に適しているでしょう。固定観念にとらわれず、新しいアイデアを生み出す力が求められる職業では、ADHDの自由な発想力が大きな強みとなります。
ADHDの特性を生かせる職種にはさまざまな選択肢がありますが、重要なのは「自分がどのようなことに興味を持ち、どの環境なら力を発揮しやすいか」を知ることです。職場環境や仕事内容が合っていれば、ADHDの特性が弱点ではなく、むしろ武器となることもあります。
不注意優勢型ADHD(旧ADD)を理解し前向きに就労に挑戦しよう
ADHDの特性のある方の中には、「自分に合った仕事が分からない」「集中力が続かず仕事が長続きしない」「職場の人間関係に自信がない」といった悩みを抱える方も多くいます。しかし、最適な仕事が見つかれば、自分の強みを生かしながら働くことが可能です。
ココルポート(Cocorport)では、ADHDの方を含め、一人ひとりに合わせた支援を通じて、適職を見つけるサポートを行っています。「どのような仕事が向いているのか分からない」という方には職業能力評価を通じて強みや得意分野を分析し、具体的な職種を提案します。また企業見学や実習を通じて、実際の仕事を体験しながら適性を見極められます。まずはお気軽にご相談ください。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
北朝霞Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
朝霞台Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
横浜Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
湘南台駅前Office
【Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)】
Officeブログ新着情報
-
目黒駅前Office 2025/04/28
【Cocorport目黒駅前Office】プログラム紹介「マシュマロパスタチャレンジ!」 -
北朝霞Office 2025/04/28
【朝霞エリア】大人の気づかい 電話対応編 -
府中駅前Office 2025/04/28
オリジナルコースターを作ろう! -
名古屋駅Office 2025/04/28
🌸🌸就職者インタビュー✨ -
大船Office 2025/04/28
大船Officeスタッフ紹介③(文房具に例えると…) -
大船Office 2025/04/28
5月のおすすめプログラム🎏 -
流山おおたかの森駅前Office 2025/04/28
🌸2025就職者インタビュー🌸第4弾🌸 -
八王子駅前Office 2025/04/28
【スタッフブログ】哲学対話プログラムってこんな感じです🔍 -
新小岩駅前Office 2025/04/28
~ココルポートに通所して~【後編】 -
尼崎Office 2025/04/28
社内報が完成しました!