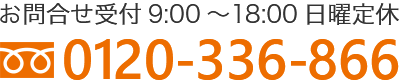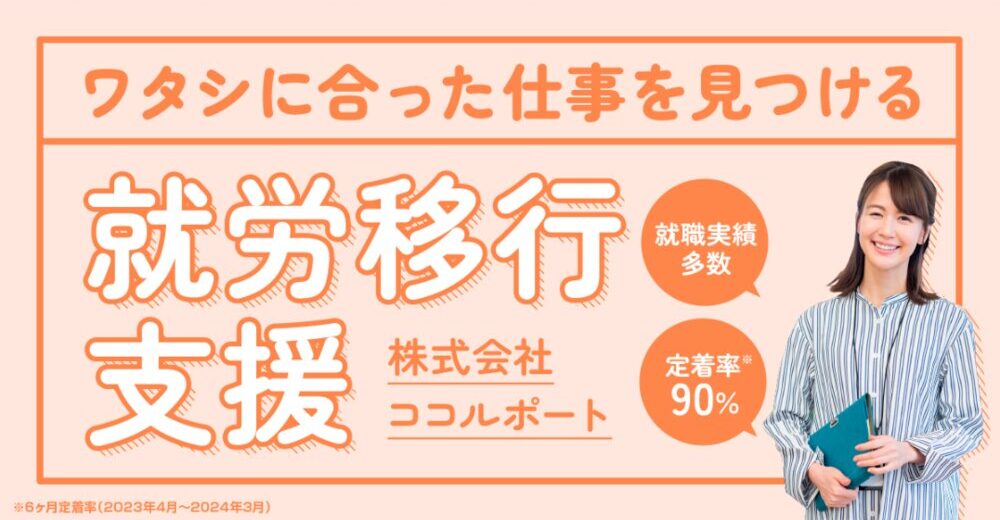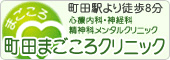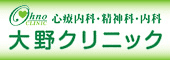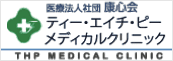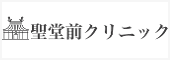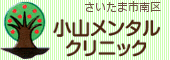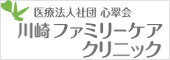- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 大人が急に吃音症になる原因とは? 症状や診断、治療方法、働くための支援について解説
大人が急に吃音症になる原因とは? 症状や診断、治療方法、働くための支援について解説
公開日:2025/04/21
更新日:2025/04/24

「話したいのに言葉が詰まる」「職場での会話が不安」など、大人になってから吃音症の症状に気づき、仕事や日常生活で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。吃音症は幼児期に発症することが一般的ですが、大人になってから突然現れるケースもあります。
本記事では、吃音症の原因や症状、診断方法を解説し、仕事で困らないための対策や支援制度についても紹介します。
目次
吃音症とは?
吃音症は、言葉をスムーズに発することが難しくなる症状です。話す際に音を繰り返したり、引き伸ばしたりする他、言葉が詰まる症状も吃音症に該当します。
幼児期に発症することが多く、成長とともに改善する場合もあれば、大人になっても続くケースもあります。精神神経疾患や発達障がいが併存する可能性も指摘されており、個々の症状や背景に応じた適切な支援が必要です。
吃音症の症状
吃音症の症状には、「連発(音の繰り返し)」「伸発(音の引き伸ばし)」「難発(言葉の詰まり)」があります。
連発は、発話の際に最初の音や単語が何度も繰り返される症状です。例えば、「た、た、たべたい」や「い、い、いそがしい」のように、最初の音が何度も続きます。
伸発は、特定の音を長く伸ばしてしまう話し方です。「あーーーしたは休み」や「そーーーれはいいね」のように、意図せず一部の音が長く発音されます。
難発は、発話の途中で言葉が止まってしまい、スムーズに話せなくなる症状です。例えば、「……ありがとう」や「……行きたい」といったように、言葉を発する前に無音の時間が生じたり、話し始めに強い力が入ったりします。
吃音症の原因
吃音症には発達性吃音と獲得性吃音があり、それぞれ異なる要因によって発症します。それぞれ詳しく見ていきましょう。
発達性吃音
幼児期に発症する吃音は「発達性吃音」といい、言葉を学び始める時期に多く見られます。発達性吃音の原因に関する理解は、時代とともに大きく変化してきました。かつては、親の接し方が吃音の原因になると考えられ、特に「愛情不足」が指摘されることがありました。
こうした考え方は、科学的根拠のない誤った情報として、現在では否定されています。
現在では、主に体質的な要因や発達的な要因、さらには周囲の環境要因が影響を及ぼしていると考えられています。
獲得性吃音
大人になってから突然発症する吃音は「獲得性吃音」といい、大きく「神経原性吃音」と「心因性吃音」の2つの種類があります。
神経原性吃音は脳の損傷や神経系の異常によって引き起こされるのに対し、心因性吃音は精神的なストレスやトラウマが原因となるとされています。
大人になってから吃音症を急に発症する原因

獲得性吃音は、主に脳や神経に問題が生じる 「獲得性神経原性吃音」 と、精神的なストレスが原因となる 「獲得性心因性吃音」 の2種類に分けられます。それぞれの特徴や発症の要因について詳しく解説します。
獲得性神経原性吃音
獲得性神経原性吃音は、脳や神経系に何らかの異常が生じたことによって発症する吃音の一種です。脳卒中や脳腫瘍、パーキンソン病、認知症などの病気によって神経の働きが損なわれることで言葉をスムーズに発音できなくなります。
また交通事故などによる頭部外傷や、特定の薬剤の影響によって発症するケースも確認されています。高齢者や、生活習慣病の人、過去に頭部に強い衝撃を受けた人などが発症しやすい傾向にあります。
獲得性心因性吃音
獲得性心因性吃音は、強い精神的ストレスや心理的なトラウマがきっかけとなって発症します。災害や事故を経験した人、過去に虐待を受けた人、職場や学校などでハラスメントにあった人などが発症することが多く、過去の出来事を思い出したり、同じような状況に置かれたりすることで症状が悪化することがあります。
年齢別に見る吃音症の特徴
吃音症は年齢によって現れ方や影響が異なり、それぞれの成長段階で異なる課題に直面します。幼児期から成人期までの特徴を理解し、適切な支援や対応を検討することが重要です。
吃音症の年齢別の特徴について詳しく見ていきましょう。
幼児期
幼児期には、話し始めたばかりの子どもに音の繰り返しや引き伸ばしといった症状が多く見られます。自分の話し方の違いに気づかないことが多いですが、親や周囲の人からの指摘、あるいは他の子どもにからかわれることで初めて意識することがあります。思い通りに言葉を発せないことでもやもやした感情を抱くこともありますが、成長とともに吃音が自然に消失するケースが多く、小学校入学前に症状がなくなることも珍しくありません。
吃音を意識するきっかけは、思い通りに話せないことへのもどかしさやフラストレーション、周囲の人からの指摘やからかいなどが影響することが多いとされています。お子さんが吃音に気づいた際には、その悩みや思いをしっかりと受け止め、「吃音は悪いことでも、恥ずかしいことでもない」と伝えることが重要です。
学童期(小学生)
学童期になると、言葉に詰まる症状が目立つようになり、自分の吃音に気づく子どもが増えます。気にせずに話す子もいれば、吃音を気にして話すことをためらったり、言葉を選んだりする子もいます。学校生活では自己紹介や発表の場面で困難を感じることがあり、周囲の理解や配慮が重要です。
学校の先生や友達に吃音について知ってもらうことで、安心して会話できる環境を整えられます。また言葉の教室など、専門的なサポートを活用するのも方法の一つです。
思春期(中高生)
思春期に入る頃には、吃音を自覚しながらも、症状を目立たせないように対処法を身に付けている場合があります。一方で、話すこと自体を避ける回避行動をとり、会話が減ることで孤立感が深まるケースも見られます。
吃音への悩みや不安がより強くなりやすく、ストレスの要因となることもあるため、親や教師など周囲のサポートに加え、相談できる専門機関やカウンセリングを利用し、安心して話せる環境を作ることが大切です。
成人期
成人期の吃音は、幼少期からの吃音が続いているケースと、大人になってから発症するケースに分類されます。社会生活では仕事の面接や会議、電話対応など、話すのを避けることが難しい場面が多いため、より大きなストレスを感じる可能性があります。
職場での理解を得たり、吃音に関する支援制度を活用したりして、より働きやすい環境を整えることが重要です。
近年、職場における吃音への理解も進みつつあり、合理的配慮の考え方が広がっています。障がい者雇用促進法では、障がいを理由とした差別の禁止とともに、合理的な配慮を行うことが義務付けられています。吃音の症状によって特定の業務が困難な場合、電話対応を減らす、発表の場面で補助を付ける、文書でのコミュニケーションを活用するなど、業務の負担を軽減する方法が考えられます。
吃音症の判断基準と受診先
吃音症は自己診断できません。言葉のつまずきが単なる一時的なものなのか、それとも治療や支援を必要とする症状なのかを判断するには、専門機関での診断を受ける必要があります。
インターネット上には自己診断のチェックリストや簡易的なテストが数多く存在しますが、参考にはできても、最終的な判断には医師の診察が必要です。
受診先は精神科や心療内科になりますが、吃音治療に強い医療機関は少ないので、注意しましょう。また発声や発語に関する問題がある場合には、耳鼻咽喉科でも診てもらえます。治療方法の章で述べるように、医師だけでなく、心理の専門家は言語聴覚士など、多職種の関わりが必要です。
さらに、小児の場合は小児科や言語聴覚士が在籍する医療機関での診察も可能です。言語聴覚士による評価を受けることで、どのような発話の特徴があるのか、どのような支援やトレーニングが適しているのかを詳しく知ることができます。ただし全ての小児科が吃音を扱っているわけではないので、受診前の確認が必要です。
吃音症の治療方法

吃音症には現在、確立された治療法はありませんが、症状を和らげる方法はいくつか存在します。適切な対応により、話しやすさを向上させることができます。吃音に悩む方がどのように改善へ向けたアプローチをすれば良いのか、詳しく見ていきましょう。
薬物療法と認知行動療法
正式に承認された薬剤はありませんが、抗精神病薬や抗うつ薬の一部は、吃音症の症状を軽減する可能性があります。しかし薬だけで治すことは難しい場合が多く、言語療法(発声・発話のトレーニング)や認知行動療法も併用して行う必要があります。
周囲の理解と環境への配慮
周囲の理解と環境への配慮は、吃音症のある方が話しやすい環境を作るために欠かせません。吃音のある方は、話すことに対する不安や緊張が増すことで症状が悪化することがあるため、周囲の人々が適切に配慮し、プレッシャーを減らすことが大切です。
話を途中で遮らずに最後まで聞く、言葉を先回りして代弁しない、急かさずに待つといった対応方法があります。
また学校や職場などで吃音を理由にからかいや差別が起きないよう、周囲への理解を促すことも必要です。
発声・発話のトレーニング
発声や発話のトレーニングなど言語療法も、吃音症の症状を和らげる方法の一つです。ゆっくりとした発声を意識することや、リズムを付けて話すことで、話しやすさが向上する場合があります。
例えば、最初はゆっくりと発声する練習を行い、徐々に自分に合った速度で話すことを目指す方法があります。
吃音症のある方が働くために大切なこと
仕事では人と話す機会が多いため、吃音の症状がストレスにつながることもありますが、話し方の工夫や環境の調整によって負担を軽減できます。吃音症のある方が働く上で重要となるポイントを紹介します。
コミュニケーションでは伝えることに意識を向ける
吃音症のある方が職場で円滑にコミュニケーションを取るためには「伝えること」に意識を向けることが大切です。会話の際に、言葉だけではなくジェスチャーや表情を活用することで、相手に意図が伝わりやすくなります。
例えば、指をさして説明したり、うなずきや手の動きを加えたりする方法があります。また電話対応やプレゼンテーションなど、吃音の影響を受けやすい業務は、上司や同僚に相談し、配置換えをお願いするのも一つの手段です。
働くための支援を受ける
吃音症のうち発達性吃音は、発達障がい者支援法の対象となる場合があります。吃音の程度によっては障がい者手帳を取得できるケースもないわけではなく、支援を受けることで職場環境を整えやすくなります。
障がい者雇用枠での就職や就労継続支援施設で働く、就労移行支援を活用するなど、選択肢が広がります。
ただし、障がい者手帳は全ての吃音症の方が取得できるわけではないため、まずは医療機関を受診し、専門家の診断を受けることが必要です。支援制度を活用することで、自分に合った働き方を見つけ、無理なく仕事を続けていけるでしょう。
吃音症で就労に悩んでいる方は「ココルポート」へご相談ください
吃音症による就労の悩みを抱えている方は、適切な支援を受けることで、安心して働く環境を整えることが可能です。吃音症の影響で仕事を探すのが不安な方や、現在の職場でコミュニケーションに困難を感じている方は、就労移行支援を活用することで、働くためのスキルや対策を学べます。
「ココルポート」は、個別支援にこだわった就労移行支援を行っています。就職活動の進め方や職場での円滑なコミュニケーション方法、ストレス管理など、多岐にわたるプログラムを用意しており、一人ひとりの状況に合わせた支援が可能です。
またeラーニングを活用することで、パソコンスキルやビジネスマナー、専門スキルを学ぶこともできます。
「話すことが苦手で面接に自信が持てない」「職場での会話に不安がある」という方も、ココルポートの支援を受けることで、自分に合った働き方を見つけられます。実際に6カ月の定着率は90%と高く、多くの方が安定して就職(復職)を果たしています。
まずは無料の見学・相談を通じて、自分に合った支援を見つけてみませんか。
監修者プロフィール
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
横浜Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
湘南台駅前Office
【Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)】 -
Cocorport Rework 横浜西口
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料) -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
湘南台駅前Office 2025/04/25
内覧会のお知らせ📢 -
蘇我駅前Office 2025/04/25
2025年5月のプログラム紹介 -
府中駅前Office 2025/04/25
🎏5月のおすすめプログラム🎏 -
横須賀第2Office 2025/04/25
「ココルポート見学体験ツアー」「個別相談会」を開催いたします!! -
千葉Office 2025/04/25
【ご案内】5月前半のプログラム予定について -
相模原橋本Office 2025/04/25
5月のおすすめプログラムのご紹介🎏【相模原橋本Office】 -
高崎駅前Office 2025/04/25
💻プログラムご紹介(模擬就労編)💻 -
日暮里Office 2025/04/25
【5月】日暮里officeお弁当&プログラム🎏 -
本八幡Office 2025/04/24
第10回!本八幡スタッフ紹介!! -
名古屋金山駅前Office 2025/04/24
🎏5月前半のプログラム🎏