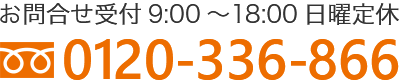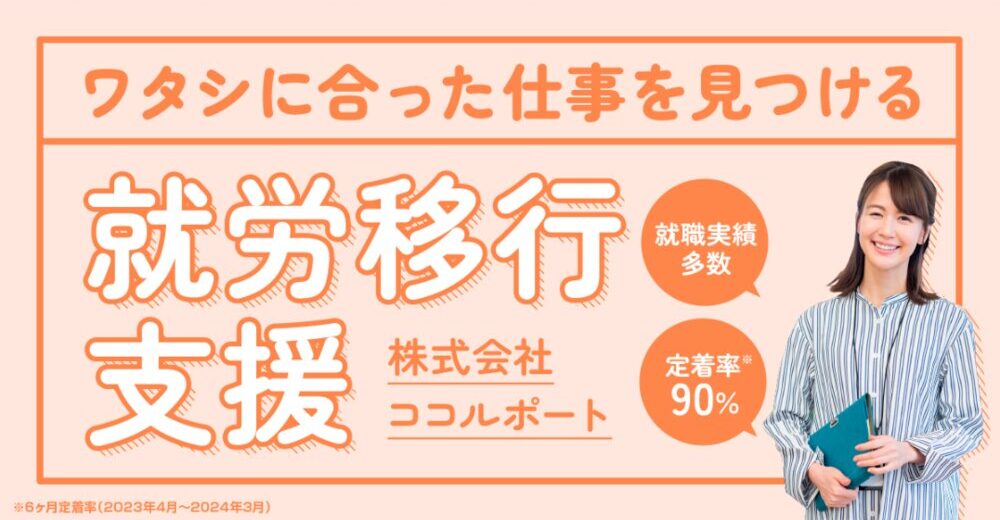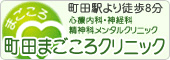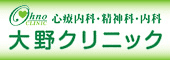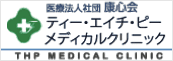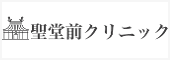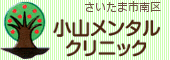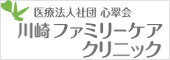- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 就労継続支援とは? A型・B型の違いや対象者、利用の流れなどを詳しく解説
就労継続支援とは? A型・B型の違いや対象者、利用の流れなどを詳しく解説
公開日:2025/04/21
更新日:2025/04/24

就労継続支援は、障がいや体調の問題で一般企業への就職が難しい方が働く機会を得るための制度です。A型とB型の2種類があり、A型は雇用契約を結んで働くのに対し、B型は雇用契約を結ばず、自分のペースで作業を行える点が特徴です。
本記事では、就労継続支援のA型・B型の違いや対象者、利用の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
就労継続支援とは?

就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方が働く準備を整えたり、働くための能力を向上させたりすることを目的とした支援制度です。
障がい福祉サービスを受けながら働く「福祉的就労」の一つであり、身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がいなど、障がいの種類を問わず支援を受けられます。
就労継続支援には、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2種類があります。
就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型は、どちらも一般企業への就職が難しい方を対象としていますが、働き方や支援の内容が異なります。最も大きな違いは雇用契約の有無です。
就労継続支援A型は、一般企業での雇用が難しいものの、一定のサポートがあれば雇用契約を結んで働ける方が対象です。利用者は事業所と雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用され、最低賃金が保証されます。
一方、就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働く形態です。体調や障がいの程度に応じて無理のない範囲で作業を行うことができ、利用者自身のペースに合わせた働き方ができます。
※参考:厚生労働省「障がい者の就労支援対策の状況」
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい方が、福祉サービスを活用しながら働く機会を得られる制度です。雇用契約を結ぶことで最低賃金が保証され、労働基準法の適用を受ける点が特徴です。対象者の条件や給与、利用期間、仕事内容について詳しく見ていきましょう。
対象者
就労継続支援A型は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がいに加え、国が指定する難病のある方が対象です。障がい者総合支援法の対象となる難病は、366種から令和6年4月に369疾病へと拡大されました。
対象年齢は原則18歳以上65歳未満です。ただし、65歳に達する前5年間に障がい福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日までに就労継続支援の支給決定を受けた場合は、引き続き就労継続支援A型を利用できます。
上記の条件を満たした上で、下記いずれかの条件を満たす必要があります。
- ・就労移行支援事業を利用したものの、一般企業等への就職ができなかった
- ・特別支援学校を卒業後、就職活動を行ったものの、一般企業等への就職ができなかった
- ・就労経験があり、現在は雇用関係がない
仕事内容
就労継続支援A型の仕事内容は事業所によって異なりますが、利用者が実務経験を積みながら一般企業への就労を目指せるような業務があります。作業内容の例は下記の通りです。
- ・パソコンによるデータ入力代行:企業や行政機関から依頼されたデータを入力する業務
- ・カフェやレストランのホールスタッフ:飲食店における接客、配膳、レジ対応、清掃などを担当
- ・封入・発送作業:企業や団体から依頼されたチラシやパンフレットを封筒に入れ、宛名ラベルを貼り、発送準備を行う作業
- ・ご当地ストラップなどのパッキング:観光地向けのお土産品やノベルティ商品の袋詰めや箱詰めを行う作業
実務を通じて職業スキルが身に付き、一般就労へのステップアップを目指せます。
給与
就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用され、最低賃金以上の給与が保障されています。
厚生労働省のデータによると、就労継続支援A型の平均工賃(月額)は83,551円で、前年の81,645円から102.3%増加し、時間額も926円から947円へと伸びています。
就労継続支援A型は雇用保険料や健康保険料、厚生年金保険料などが給与から差し引かれ、その後の金額が手取りです。そのため、実際に受け取る金額は、月額工賃の額面とは異なる場合があることを理解しておくことが大切です。
加えて、給与額は地域の最低賃金や事業所の方針、勤務時間によっても異なるため、あくまで目安としましょう。
※出典:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」
利用期間
就労継続支援A型の利用期間には明確な上限がなく、雇用契約が続く限り働き続けられます。しかし、事業所ごとに契約内容は異なり、多くの事業所では一定期間ごとに契約更新が行われています。そのため、契約書に記載されている雇用期間や更新の条件について確認しておくことが大切です。
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに作業を行うため、最低賃金の適用はありませんが、体調や生活リズムに合わせて働く時間や作業量を調整できる点が特徴です。対象者の条件や給与(工賃)、利用期間、仕事内容について詳しく見ていきましょう。
対象者
就労継続支援B型の対象者には年齢制限がなく、一定の条件を満たす方が利用できます。対象条件は下記の通りです。
- ・就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業への就職が難しくなった
- ・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された
- ・上記に該当しないが、50歳以上の方、または障がい基礎年金1級を受給している
加えて、特別支援学校の卒業後に就労継続支援A型を利用する場合は、自治体によっては「就労移行支援を利用してアセスメントを受けることが必須」のような別途条件が定められています。事前に自治体の福祉窓口で確認することが大切です。
仕事内容
就労継続支援B型の作業内容は事業所によって異なりますが、利用者の特性や能力に合わせた業務が用意されています。作業内容の例は下記の通りです。
- ・ハーブや花の栽培・加工:温室や屋外でハーブや花を育て、収穫後に乾燥や袋詰めを行う作業
- ・リサイクル素材の選別・分別:古紙や金属、プラスチック製品などのリサイクル資源を種類ごとに仕分ける作業
- ・カフェの運営補助:店内での接客や食器洗い、簡単な調理補助などを行う業務
- ・チラシの折り込み・封入作業:企業や店舗が配布するチラシを折ったり、封筒に入れたりする作業
就労継続支援B型の作業は、利用者が無理なく取り組めるよう配慮されており、作業時間やペースも調整可能です。
給与
就労継続支援B型の給与(工賃)は、一般的な雇用とは異なり、労働の対価としての給与ではなく、作業に対する報酬として支払われます。そのため、最低賃金の適用はなく、事業所ごとに工賃の金額が異なる点が特徴です。
厚生労働省のデータによると、令和4年度における就労継続支援B型事業所の平均工賃(月額)は17,031円であり、前年の16,507円から103.2%増加しました。また、時間額に換算すると243円で、前年の233円から104.3%増加しています。
工賃は事業所の経営状況や生産活動の規模、受注状況によって大きく左右されるため、工賃の金額だけではなく、作業内容や環境、自身のライフスタイルに合った支援が受けられるかどうかも重要なポイントです。
※出典:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」
利用期間
就労継続支援B型には利用期間に特別な制限が設けられておらず、利用者の状態や体調に合わせて柔軟に働くことが可能です。例えば、1日1時間だけ作業を行ったり、週1日だけ通所して無理のない範囲で作業を続けたりすることも認められています。
就労継続支援A型のメリット・デメリット
就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶため、給与の保障や労働基準法の適用を受ける一方で、一般就労とは異なる制約や課題も存在します。就労継続支援A型のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット
就労継続支援A型を利用するメリットは、雇用契約を結ぶことで最低賃金が保証されることです。一般的なパートやアルバイトと同様に労働基準法が適用されるため、一定の安定した収入を得られます。加えて、労働時間や就業条件が明確に定められているため、予測可能な働き方ができる点も魅力です。
また残業が少なく、働きやすい環境が整っていることもメリットです。利用者の健康や負担を考慮し、基本的に労働基準法の範囲内での勤務が求められます。一般企業のように長時間労働が発生することは少なく、無理のない範囲で働きながら、徐々に仕事のリズムを作っていくことが可能です。
デメリット
就労継続支援A型には一般就労に向けた訓練が少ない傾向にあるという点にデメリットを感じる方もいるでしょう。A型事業所の目的は、利用者が働きながら一定の収入を得ることであるため、就職のサポートは少ないケースが多いです。
また、仕事の種類や業務内容が限定されることもデメリットです。A型事業所で提供される業務は、軽作業や事務作業、清掃業務などが多いです。その他の職種への転職を考えている場合は、別途、職業訓練や就労移行支援を活用することも検討しましょう。
就労継続支援B型のメリット・デメリット
就労継続支援B型は、一般就労が難しい方が無理のない範囲で働きながら社会参加を続けられる制度です。自由度の高い働き方ができる一方で、工賃の低さなどの課題もあります。ここでは、就労継続支援B型のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット
就労継続支援B型の大きなメリットは、自分の体調や生活リズムに合わせて柔軟に働けることです。週に1回や半日のみの利用といった短時間の勤務も可能で、体調に不安がある方や、継続的な就労に自信がない方でも無理なく働けます。
またスキルアップの場として活用できる点もメリットです。軽作業や農作業、飲食関連の業務、手工芸などさまざまな仕事があるため、作業を通じて新しい技術を習得できます。
デメリット
就労継続支援B型のデメリットとしてまず挙げられるのは、工賃が低いため、生活費をまかなうほどの収入を得るのが難しいことです。B型では雇用契約を結ばないため、最低賃金の適用がなく、労働の対価ではなく作業報酬として工賃が支払われます。また業務内容が限られることがある点もデメリットです。
就労継続支援を利用する手続きの流れ

就労継続支援A型・B型を利用するには、事前に自治体の手続きを行い、受給者証を取得する必要があります。ここでは、利用開始までの具体的な流れを解説します。
1.就労継続支援事業所を探す
まずは、自分に合った就労継続支援事業所を見つけることが大切です。事業所を探す方法はいくつかあり、市区町村の障がい者支援窓口やハローワークに相談する他、インターネットでも検索できます。
また地域の相談支援事業所や障がい者就業・生活支援センターなどに相談することで、自分に合った事業所を紹介してもらうこともできます。
事業所を見つけたら、実際に訪問して現場の雰囲気や作業内容を確認することが重要です。どのような仕事を行うのか、職員の支援体制はどうなっているのか、通いやすい場所かどうかなど、自分に合った環境かをしっかり見極めましょう。
2.就労継続支援事業所の選考を受ける(就労継続支援A型のみ)
就労継続支援A型を利用する場合、一般の就職と同様に事業所との雇用契約を結ぶ必要があるため、選考が行われます。履歴書の提出や面接を経て、事業所側の判断によって採用の可否が決まります。
選考の具体的な内容は事業所によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。面接では、働く意欲やこれまでの経験、希望する働き方などを聞かれることが多く、事業所によっては簡単な作業テストを実施する場合もあります。
採用が決まった場合は、自治体の窓口で正式な手続きを進めます。
3.自治体の窓口で申請をする
就労継続支援A型・B型を利用するには、自治体の障がい福祉窓口で「障がい福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。受給者証は、福祉サービスを利用するための正式な証明書です。
まず、自治体の窓口で申請手続きを行い、心身の状態や生活環境についての聞き取り調査を受けます。障がいの程度や現在の就労状況、希望するサービスの内容などが確認され、利用者にとって最適な支援が提供できるように調整されます。
また「サービス等利用計画案」を作成して提出が必要です。
申請が受理されると自治体が審査を行い、諸条件を満たしていれば「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。審査には1カ月以上かかることもあるため、利用を希望する場合は早めに手続きを進めることが重要です。
就労継続支援の利用者負担
就労継続支援は障がい者福祉サービスの一環として提供されており、利用者は一定の自己負担が発生します。ただし、負担額には所得に応じた上限が設定されており、どれだけサービスを利用しても上限額以上の費用がかかることはありません。
就労継続支援の利用者負担上限額(1カ月当たり)は下記の通りです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(※2) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外(※3) | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障がい者基礎年金1級を受給している場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
(※2)収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」に分類。
※出典:厚生労働省「障がい者の利用者負担」
就労継続支援と就労移行支援・就労定着支援との違い
就労に関する福祉サービスには、就労継続支援A型・B型の他に、就労移行支援や就労定着支援があります。それぞれ目的や利用できる対象者、提供されるサポート内容などに違いがあります。
ここでは、就労継続支援と就労移行支援・就労定着支援の違いについて詳しく解説します。
就労移行支援との違い
就労移行支援は、障がいのある方が一般企業への就職を目指すための訓練を受けることを目的とした支援制度です。就労継続支援が「福祉的な働く場を提供すること」に重点を置いているのに対し、就労移行支援は「一般就労に必要なスキルを習得し、企業での雇用につなげること」が主な目的です。
支援を利用することで、働くための知識やスキルを身につけるだけではなく、職場体験や実習を通じて適性に合った仕事を見つける機会が得られます。また、就職活動のサポートや履歴書作成・面接対策などの支援も行われます。
対象となるのは、18歳以上65歳未満の方で、一般就労に向けたトレーニングが必要な人です。また、65歳に達する前の5年間に障がい福祉サービスの支給決定を受けており、65歳の誕生日の前日までに就労移行支援の支給決定を受けた場合は、65歳以降も継続利用が可能です。
就労定着支援との違い
就労定着支援は、一般企業に就職した後も安定して働き続けられるようサポートを行う制度です。就労移行支援や就労継続支援A型・B型とは異なり、働き始めた後の課題に焦点を当てた支援が提供されます。
障がいのある方が一般就労へ移行した後、職場環境の変化や新しい業務への適応、生活リズムの調整などに戸惑うことは少なくありません。就労定着支援では、こうした職場や生活面での課題を解決し、長く働き続けられるように支援することを目的としています。
支援を利用できるのは、就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を経て一般就労へ移行し、就職後6カ月が経過した障がいのある方です。
就労継続支援を利用するかどうかを迷ったら「ココルポート」へご相談ください
就労継続支援A型・B型は、一般企業での就労が難しい方に向けた重要な支援制度です。それぞれのメリットやデメリットを踏まえ、利用を検討しましょう。
ココルポートの就労移行支援は個別支援にこだわり、一人ひとりに合ったサポートを提供しています。パソコンスキルやビジネスマナー、コミュニケーションなど555種類以上のプログラムがあり、5,000本以上のeラーニング動画で学習も可能です。通所は週1日からOKで、交通費補助やランチ支援もあります。2023年度の就職(復職)者は762名、6カ月定着率90%と高い実績を誇ります。まずはお気軽にご相談ください。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
横浜Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
湘南台駅前Office
【Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)】 -
Cocorport Rework 横浜西口
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料) -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
大阪千里中央駅前Office 2025/04/24
プログラムのご紹介【お花見に行こう🌸】 -
京都駅前Office 2025/04/24
個別訓練ツール紹介 第1弾! -
川越Office 2025/04/24
ココルポートでの様々な作業のご紹介(DM作業) -
横須賀Office 2025/04/24
「ココルポート見学体験ツアー」「個別相談会」を開催いたします!! -
Cocorport Rework 船橋 2025/04/24
ご利用対象の方って? -
川越第3Office 2025/04/24
新年度が始まりました! -
北千住Office 2025/04/24
【5月開催プログラム紹介】人狼ゲーム🐺 -
北千住Office 2025/04/24
【プログラム内容&感想】アサーショントレーニング~自分も相手も大切にする伝え方~ -
勝田台駅前Office 2025/04/24
5月おすすめプログラム✨ -
京都四条河原町駅前Office 2025/04/24
★スタッフ紹介④★