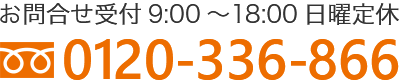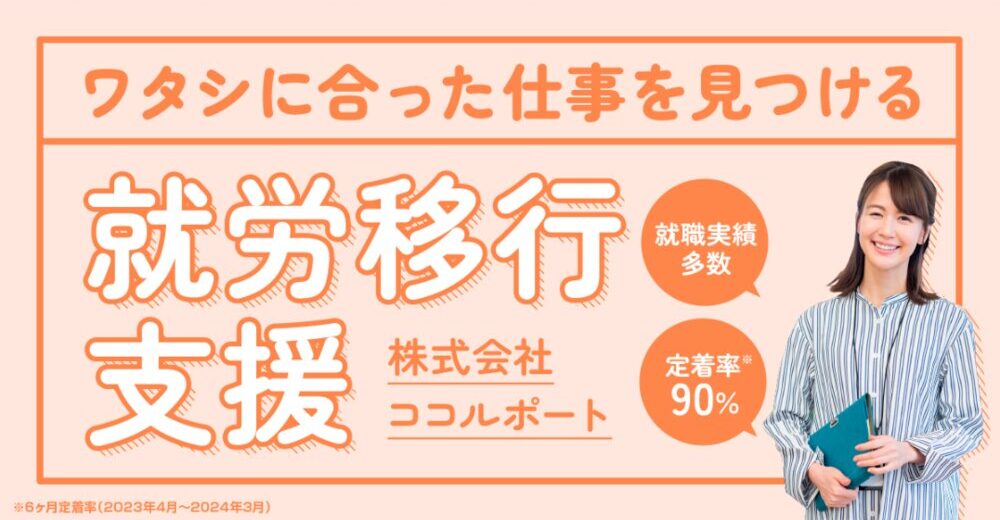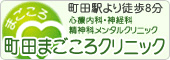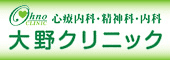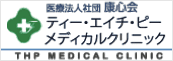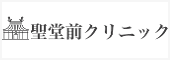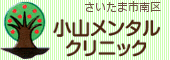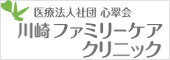- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 療育手帳とは? 申請方法からメリット・デメリット、受けられる就労支援まで徹底解説
療育手帳とは? 申請方法からメリット・デメリット、受けられる就労支援まで徹底解説
公開日:2025/04/21
更新日:2025/04/24

療育手帳は、知的障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要になることがある手帳です。「どのような手続きで取得するのか」「どのような支援が受けられるのか」「取得にあたってのデメリットはあるのか」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
本記事では、療育手帳の基本的な役割から申請の流れ、取得することのメリット・デメリット、さらに就労をサポートする制度について詳しく解説します。
目次
療育手帳とは?
療育手帳は、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。福祉サービスを受けるための証明書としての役割があり、障がい者総合支援法に基づく福祉サービスや、各自治体・民間事業者が提供するさまざまなサポートを受けられます。
療育手帳制度の目的は、知的障がいのある方への一貫した指導や相談を行うとともに、教育・就労・医療・生活支援など、必要な援助を円滑に受けられるようにすることです。
自治体によっては「愛の手帳」「愛護手帳」などと呼ばれる
療育手帳は全国共通の制度ですが、自治体によって名称が異なる場合があります。
東京都や横浜市では「愛の手帳」、名古屋市や青森県では「愛護手帳」と呼ばれています。名称が違っても、目的や制度内容は同じで、各自治体が定める支援サービスを利用する際に必要です。
療育手帳の取得方法や支援内容は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの地域の窓口で確認しましょう。
療育手帳の対象者
療育手帳の対象となるのは、18歳以前に知的機能の障がいが認められ、それが持続している方です。幼少期から知的発達の遅れが見られた方や、18歳までに疾患やけがによって知的機能に障がいが生じた方が該当します。
多くの自治体では、知能指数(IQ)が75以下(または70以下)を基準とし、日常生活や社会生活に支障がある場合に交付されます。
※参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」
発達障がいのある場合も療育手帳の対象になる?
発達障がいがある方は、知的障がいを伴うと診断された場合は療育手帳の申請対象です。知的障がいがない場合は療育手帳ではなく、精神障がい者保健福祉手帳の申請対象となることがあります。
障がい者手帳には、大きく分けて身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の3種類があります。
身体障がい者手帳は、身体機能に一定の障がいがあると認定された方に交付されるものです。対象の障がいは、視覚障がいや肢体不自由、肝機能障がいなどです。
精神障がい者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、発達障がいなどの精神疾患が一定の程度に達している場合に交付されます。1級から3級までの等級があり、障がいの状態に応じて支援を受けられます。
療育手帳の等級と判断基準
療育手帳には、知的障がいの程度に応じた等級が設けられています。判定は児童相談所(18歳未満の方)または知的障がい者更生相談所(18歳以上の方)で行い、知能指数(IQ)や日常生活における支援の必要性などを総合的に判断して決定します。
療育手帳の等級と判断基準について、詳しく見ていきましょう。
療育手帳の等級
療育手帳には、A判定(重度)とB判定(軽度~中等度)の2つの等級があり、障がいの程度によって判定が異なります。A判定は、日常生活での支援が必要な重度の知的障がいのある方で、B判定は比較的軽度または中等度の知的障がいがある方です。
自治体によってはB判定をさらに細分化し、「B1(中等度)」と「B2(軽度)」に分けるケースもあります。
療育手帳の判断基準
等級の判定は、知能指数(IQ)だけではなく、日常生活での支援の必要度や社会適応能力なども考慮されます。A判定とB判定(B1、B2)の具体的な基準について詳しく解説します。
■A判定の判断基準
療育手帳は、児童相談所または知的障がい者更生相談所で知的障がいの判定を受けた場合に交付されます。知的障がいの程度に応じて「重度(A)」と「それ以外(B)」の2つの区分が設けられています。
重度(A)に該当するのは、知能指数(IQ)がおおむね35以下であり、下記に該当する方です。
- ・着脱衣、食事、排便、洗面など、日常生活の介助を必要とする方
- ・異食・興奮などの問題行動が見られる方
また知能指数がおおむね50以下で、盲・ろうあ・肢体不自由などがある方も重度(A)に分類されます。
※参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」
■B判定(B1、B2)の判断基準
B判定以降の分け方は自治体によって異なります。ここでは、堺市の療育手帳の判断基準を紹介します。
18歳未満におけるB判定(B1)の判断基準の一例は下記の通りです。
- ・知能指数(IQ)または発達指数が36~50の方で、社会生活の能力が中等度以上。日常生活において、ある程度の介助・介護を必要とする場合や、ほとんど介助を必要としない場合
- ・知能指数(IQ)または発達指数が51~75の方で、社会生活の能力が重度以下。日常生活での介助が多少必要な場合
B判定(B1)には、他にも知能指数別に要件が定められています。
18歳未満におけるB判定(B2)の判断基準は下記の通りです。
- ・知能指数(IQ)または発達指数が51~75の方で、社会生活の能力が中等度以上。行動面や医療的なケアである程度の介助が必要、またはほとんど介助が必要ない場合
※参考:堺市「堺市療育手帳に関する要綱」
療育手帳の申請・交付の流れ

療育手帳を取得するには、申請から判定、交付までの手続きを踏む必要があります。手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認することが大切です。以下では、一般的な申請から交付までの流れを解説します。
申請
まずは、お住まいの自治体の福祉窓口で申請が可能か相談することから始めます。申請が認められた場合、必要な手続きを確認し、指定された書類を揃えて提出します。主な必要書類として、申請書、本人確認書類(マイナンバーカードや保険証など)、顔写真(縦4cm×横3cm)、印鑑などが求められることが一般的です。自治体によっては追加の書類が必要になることもあるため、詳細は事前に確認しておくとスムーズです。
また2022年6月から療育手帳の情報とマイナンバーが紐づけられるようになり、申請時に個人番号の提示が求められることがあります。
判定
判定を受ける際には、申請時に予約を取ります。療育手帳の判定を受ける場所は、下記のように年齢で異なります。
- ・18歳未満:児童相談所
- ・18歳以上:知的障がい者更生相談所
当日は、小児科医や精神科医、心理判定員、小児科医などが知的障がいの程度を判定する検査を行います。検査内容の一例は下記の通りです。
- ・幼少期からの発達状況や知的機能の状態を確認するための知能検査や心理検査
- ・本人との面談
- ・保護者からの聞き取り
医療機関や学校の記録などの客観的な資料も参考にしながら総合的に判断されます。本人が直接面談を受けることが難しい場合には、保護者や主治医の意見を元に判定することもあります。
交付
判定結果を元に審査が行われ、療育手帳の交付可否と等級が決定されます。申請から交付までの期間は、おおよそ2カ月です。手帳の交付が認められた場合、指定された窓口(福祉課や福祉保健センターなど)で手帳を受け取ります。
療育手帳に更新期限はある?
療育手帳は一定期間ごとに更新(再判定)が必要です。更新頻度や手続き方法は自治体によって異なり、再判定が必要な場合と、不要とされる場合があります。
手帳に記載された次回判定年月日を確認の上、必要に応じて更新の手続きを進めましょう。
再判定の頻度は年齢によって異なり、18歳未満の方は児童相談所でおおむね2~4年ごと、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所でおおむね10年ごとが一般的です。ただし、自治体によっては障がいの等級に関わらず再判定を省略し、「判定不要」として更新手続きを不要とする場合もあります。
詳しくは、お住まいの自治体の障がい福祉窓口で確認しましょう。
再判定手続きには、以下の書類が必要になることが多いものの、市区町村によって異なります。
- ・再判定(再交付)申請書(自治体窓口で配布)
- ・現在の療育手帳
- ・印鑑(自治体によっては不要)
- ・顔写真(縦4cm×横3cm)
療育手帳を取得するメリット
療育手帳を取得することで、障がいの証明となるだけではなく、さまざまな支援や福祉サービスを受けられます。
適用される支援内容は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の福祉課や公式サイトを確認しましょう。
ここでは、療育手帳を取得するメリットについて解説します。
医療費の助成や公共機関の割引
療育手帳を持っていると、医療費の一部助成や公共機関の運賃割引といった経済的支援を受けられます。例えば以下のような支援があります。
- ・医療費の助成
- ・公共交通機関の割引
- ・公共施設の利用料割引
- ・通信費の割引
- ・公営住宅の優先入居
- ・NHK受信料の減免
助成内容や適用条件は自治体ごとに異なるため、詳細は市町村の福祉窓口で確認しましょう。
年末調整の障がい者控除
療育手帳を持っていると、税制面での優遇措置も受けられます。その一つが障がい者控除で、所得税や住民税の負担を軽減できます。
療育手帳の等級が重度(A相当)の場合、「特別障がい者」として認定され、通常の障がい者控除よりも控除額が増額されます。控除額は下記の通りです。
| 障がい者区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
| 障がい者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障がい者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障がい者 | 75万円 | 53万円 |
※参考:国税庁「障がい者と税」
※参考:東京都「個人住民税」
自動車税などの控除
療育手帳を持つことで、自動車税や自動車取得税の控除や減免措置を受けられる場合があります。
適用される条件の例は下記の通りです。
- ・本人が自ら運転する
- ・本人と同居しており生計を共にする家族が、本人の通院・通学・通勤のために運転する
減免を受けるには、申請が必要です。お住まいの都道府県の税務窓口で詳細を確認し、申請手続きを進めましょう。
療育手帳を取得するデメリット

療育手帳は、取得そのものにデメリットはないものの、申請手続きに手間がかかります。また、心理的な負担を受ける場合があります。
療育手帳を取得することで、周囲の目が気になったり、就職や進学の際に不安を感じたりすることもあるでしょう。
療育手帳を所持している方向けの採用枠や就労支援サービス
ここからは、療育手帳を所持している方向けの採用枠や受けられる就労支援サービスを紹介します。
障がい者採用枠
障がい者採用枠は、障がい者雇用促進法(障がい者雇用促進法43条第1項)に基づき、企業が一定割合の障がい者を雇用するために設けている採用枠です。2025年時点では、全従業員のうち2.5%は障がい者を雇用することが義務づけられています。
企業側に障がいに対する理解があるため、業務の進め方や職場環境の調整が期待できます。また障がい者専用の人事担当者が配置されている企業も多く、困ったときに相談しやすいのもメリットです。
※参考:厚生労働省「事業主の方へ」
■一般採用枠との違い
一般採用枠では、障がいを企業に伝えずに就職することが可能ですが、周りの人による配慮を得られない場合があります。
一般採用枠のメリットとデメリットは下記の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・職種や企業の選択肢が多い
・昇進や昇給の機会が豊富 |
・周囲と同じ作業ペースを求められる
・障がいを公表していないため、体調面の相談がしにくい |
周囲に障がいが気付かれないケースも多く、職場環境によっては負担が大きくなる可能性があります。そのため、職場選びの際には、業務内容や職場の雰囲気、サポート体制を確認することが大切です。
公共職業安定所(ハローワーク)
ハローワークには、障がいのある方を対象とした専用の相談窓口が設けられており、就職活動のあらゆる面で支援を受けられます。専門の職員が就職に関する相談や適性に合った求人の紹介、履歴書や職務経歴書の作成アドバイス、面接対策など、就職に向けた準備を総合的にサポートします。
また、職業訓練の案内の他、各種セミナーや就職支援プログラムも開催されており、個々の状況に合わせた支援が受けられる点が特徴です。
※参考:ハローワークインターネットサービス「障がいのある皆様へ」
地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターは、障がいのある方が安定した職業生活を送るための支援を行う専門機関です。就職に向けた実践的な訓練が受けられる他、職業適性検査を通じて、自分に合った仕事を見つけるサポートを受けられます。
作業トレーニングや職場実習を通じて、実際の職場環境に近い形で経験を積むことが可能です。また、専門の職業カウンセラーが個別のリハビリテーション計画を作成し、就職までの道筋を明確にするサポートを行います。
※参考:独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構「地域障がい者職業センター」
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障がいのある方が働くための準備を整え、スムーズに就職できるようサポートを行う施設です。就職に不安を感じる方に向けて、模擬就労や職場体験の機会を提供し、働く環境に少しずつ慣れていけるよう支援を行います。
ビジネスマナーや業務スキルを学べる研修の他、履歴書の作成や面接の練習もあります。また就職後の職場定着支援もあり、働き始めた後も安定して仕事を続けられるよう、助言を受けられます。
就労継続支援事業所
就労継続支援事業所は、一般企業への就職が難しい方に対し、働く機会を提供する福祉サービスです。利用者の状況や働き方に応じて、A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2つの種類があります。
就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を結ぶ仕組みになっており、労働基準法が適用されます。これにより、最低賃金以上の給与が保証され、安定した収入を得ながら働けます。
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働くスタイルです。給与の代わりに「工賃」が支払われ、利用者は自分のペースで作業を行えます。B型は、体力的・精神的な理由から長時間の就労が難しい方や、一般企業での就職が困難な方に適しています。
療育手帳の申請方法やメリットを理解して就労に生かそう
療育手帳は、知的障がいのある方が必要な支援を受け、より良い生活を送るための手帳です。医療費の助成や税制面での優遇、公共交通機関の割引など、生活を支えるさまざまな制度が利用できる他、就労支援の面でも障がい者採用枠への応募や合理的配慮を受けながらの就労が可能になります。
しかし、新しい環境に踏み出すことに不安を感じる方も多いかもしれません。そのような方々を支えるのがココルポートです。
単なる就職支援にとどまらず、その先の自立した生活まで見据えた包括的なサポートを行っています。スキル向上のための555種類以上のプログラムを用意し、一人ひとりに適した進路を共に考えていくことを大切にしています。2023年度には762名が就職し、就職後の定着率は90.0%と高い実績を誇ります。
週に1~2回の通所から無理なくスタートし、徐々にステップアップしていくことが可能です。自分に合った働き方を見つけ、安心して新たな一歩を踏み出したい方は、まずはお気軽にご相談ください
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
日暮里Office
🌸🌸日暮里office🌸🌸 事業所説明&見学について!! -
北朝霞Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
朝霞台Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
横浜Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中
Officeブログ新着情報
-
武蔵浦和Office 2025/04/29
通所2ヶ月後インタビュー! -
目黒駅前Office 2025/04/28
【Cocorport目黒駅前Office】プログラム紹介「マシュマロパスタチャレンジ!」 -
北朝霞Office 2025/04/28
【朝霞エリア】大人の気づかい 電話対応編 -
府中駅前Office 2025/04/28
オリジナルコースターを作ろう! -
名古屋駅Office 2025/04/28
🌸🌸就職者インタビュー✨ -
大船Office 2025/04/28
大船Officeスタッフ紹介③(文房具に例えると…) -
大船Office 2025/04/28
5月のおすすめプログラム🎏 -
流山おおたかの森駅前Office 2025/04/28
🌸2025就職者インタビュー🌸第4弾🌸 -
八王子駅前Office 2025/04/28
【スタッフブログ】哲学対話プログラムってこんな感じです🔍 -
新小岩駅前Office 2025/04/28
~ココルポートに通所して~【後編】